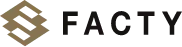technical-tips
ベルトの張力計算ガイド
ベルト張力計算ガイド|フラットベルトとタイミングベルト
本ガイドは、ベルト張力計算時に「どの式をいつ使えばよいか」を最短で理解できるように構成しました。コンベア搬送に使うフラットベルトと、動力伝達に使うタイミングベルトを対象に、式の意味→手順→代表例→実務チェックの順で解説します。単位は SI(N, kg, m, s)。
まずはここだけ覚える3式
- ベルト速度:プーリ直径 d[m]、回転数 n[rpm] で
![Rendered by QuickLaTeX.com \[ v=\frac{\pi d n}{60} \quad\text{(タイミング:}\;v=\frac{p z n}{60}\text{)} \]](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20154%2036%22%3E%3C/svg%3E)
- 有効張力:伝達動力 P[W] と速度 v[m/s] で
![Rendered by QuickLaTeX.com \[ T_e=\frac{P}{v} \]](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2058%2037%22%3E%3C/svg%3E)
- 張力の関係(フラットベルトの基礎)
![Rendered by QuickLaTeX.com \[ \frac{T_1}{T_2}=e^{\mu\theta},\qquad T_1-T_2=F,\qquad T_i=\frac{T_1+T_2}{2} \]](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20348%2039%22%3E%3C/svg%3E)
※ここで
 は必要駆動力(ベルトがワークを動かすために必要な力)です。
は必要駆動力(ベルトがワークを動かすために必要な力)です。
用語と記号(やさしい定義)
- P:伝達したい動力 [W](モータの有効出力)
- v:ベルト速度 [m/s](1秒で進む距離)
- T_1, T_2:張り側/ゆるみ側のベルト張力 [N]
- T_i:初期張力 [N](停止中でも与える「下ごしらえ」の張力)
 :ベルトとプーリの摩擦係数(すべりやすさの指標)
:ベルトとプーリの摩擦係数(すべりやすさの指標) :巻き付け角 [rad](ベルトがプーリに接している角度)
:巻き付け角 [rad](ベルトがプーリに接している角度) :コンベアの摩擦係数(搬送物と滑り台など)
:コンベアの摩擦係数(搬送物と滑り台など)- m:搬送質量 [kg]、g:9.81 m/s²
目安値
| 項目 | よく使う目安 |
|---|---|
| ベルト/プーリ摩擦 | 0.20〜0.35(ゴム×鋼) |
| 搬送摩擦 | 0.05〜0.15(ローラ支持)/0.2〜0.4(滑り台) |
| 巻き付け角 | できれば ≥ 180°(最低でも ≳120° を目安) |
| サービス係数 | 1.0〜1.2(定常)/1.3〜1.5(中衝撃)/1.6〜2.0(重衝撃) |
フラットベルト(コンベア)の計算手順
対象:水平・定速が基本。必要に応じて「勾配」「加減速」を足し算します。
- 必要駆動力
 を出す(基本形:水平・定速):
を出す(基本形:水平・定速):![Rendered by QuickLaTeX.com \[ F = m g \,\mu_c \]](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2082%2016%22%3E%3C/svg%3E)
勾配角
 があれば
があれば  を加算、加速中は
を加算、加速中は  も加算:
も加算:![Rendered by QuickLaTeX.com \[ F_{\text{総}} = m g(\mu_c + \sin\alpha) + m a \]](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20196%2019%22%3E%3C/svg%3E)
- 張力比を計算:

- 張力分配:

- 軸荷重の目安:
 (軸受・フレーム強度の確認)
(軸受・フレーム強度の確認) - ベルト幅の確認:メーカーの「許容線張力(N/mm)」で
 を満たす幅か確認
を満たす幅か確認
代表計算例(水平・定速)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 搬送質量 | 50 kg |
| コンベア速度 | 20 m/min = 0.333 m/s |
| 駆動プーリ径 | 200 mm(参考) |
| 摩擦(搬送) | |
| 摩擦(ベルト/プーリ) | |
| 巻き付け角 |
- 必要駆動力

- 張力比

- 張力
 ,
, 
- 初期張力

- (参考)軸へのトルク

- (軸荷重)

バリエーション(現場で足し引きするだけ)
- 勾配 5°:追加

- 加速 0→0.333 m/s を 0.5 s:
 → 追加
→ 追加 
- 合計すると
 。
。
同じ手順で を再計算(計算フローはそのまま)。
を再計算(計算フローはそのまま)。
タイミングベルト(動力伝達)の計算手順
歯で噛み合うため、基本的にすべりがなく「動力から張力を逆算」します。
- ベルト速度:ピッチ p[mm]、駆動歯数 z
![Rendered by QuickLaTeX.com \[ v=\frac{p z n}{60} \]](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2064%2032%22%3E%3C/svg%3E)
- 有効張力:

- サービス係数を掛ける:

- 初期張力:

- トルク確認:
 (=
(=  でも可)
でも可) - 幅選定:メーカーの「許容有効張力(N/幅)」または「許容動力表」で確認
代表計算例(T5, 20歯×1500 rpm, 0.75 kW)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ピッチ形状 | T5 |
| ベルト幅 | 20 mm(候補) |
| モータ出力 | 0.75 kW |
| 回転数 | 1500 rpm |
| 駆動/従動歯数 | 20/40 |
| 駆動ピッチ円径 | |
| サービス係数 |
- ベルト速度

- 有効張力

- 張力

- 初期張力

- トルク
 (9550式でも同値)
(9550式でも同値) - (軸荷重の目安)

張力調整の実務ポイント(初心者がつまずきやすい所)
- 初期張力が低い→フラットはすべり、タイミングは歯飛び/騒音→軸受・ベルト寿命低下。
- 測り方:テンションゲージや振動法(スマホアプリ含む)で実測。メーカー推奨値±10%を目安。
- 再調整:初期伸び・温度で変化するため、試運転後にもう一度張る。
- 巻き付け角の確保:不足時はスナバー(当てローラ)で角度を稼ぐ。
- 噛合歯数:最低 6 歯目安(仕様に従う)。プーリ径が小さすぎると寿命低下。
コピペ用:式まとめ(単位つき)
- 速度(直径):
![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle v=\frac{\pi d n}{60}\;\,[{\rm m/s}]](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20114%2036%22%3E%3C/svg%3E)
- 速度(ピッチ):
![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle v=\frac{p z n}{60}\;\,[{\rm m/s}]](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20112%2032%22%3E%3C/svg%3E)
- 有効張力:
![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle T_e=\frac{P}{v}\;\,[{\rm N}]](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%2088%2036%22%3E%3C/svg%3E)
- フラット張力比:
 ,
,  ,
,  ,
, 
- 必要駆動力(水平/勾配/加速):

- トルク:
![Rendered by QuickLaTeX.com \displaystyle M=T_e\frac{d}{2}=\frac{9550\,P_{\rm kW}}{n_{\rm rpm}}\;\,[{\rm N\,m}]](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20viewBox=%220%200%20220%2043%22%3E%3C/svg%3E)
よくあるミスと回避法
 を満たしていない(フラット)→張力比と同時に必ず確認。
を満たしていない(フラット)→張力比と同時に必ず確認。- 直径 d ではなくピッチ円径を使うべき所で外径を使ってしまう(タイミング)。
- 単位混在(mmとm、minとs)→冒頭で必ず揃える。
 (プーリ摩擦)と
(プーリ摩擦)と  (搬送摩擦)を取り違える。
(搬送摩擦)を取り違える。
まとめ|設計の流れチェックリスト
- 用途を決める(搬送=フラット/動力=タイミング)
- 速度 v と必要力/動力(F または P)を見積もる(勾配・加減速も)
- 式で
 を算出(フラットは
を算出(フラットは  を確認)
を確認) - 幅・巻き付け角・噛合歯数をメーカー表で確認
- 軸受荷重
 とフレーム強度を確認
とフレーム強度を確認 - 据付後に初期張力を実測し、試運転後に再調整