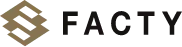technical-tips
材料の熱膨張(材料特性)について
材料の熱膨張ガイド(装置設計者向け)
装置設計では材料の熱膨張を正しく見積もることが、クリアランス管理や精度保証の要となります。特に高精度な位置決め装置や成形金型など、温度変化による寸法誤差が製品品質に直結するケースでは、熱膨張を軽視できません。
この記事では、鉄・銅・アルミ・ステンレス・MCナイロンといった代表材料の線膨張係数と計算方法を解説し、SKD金型を例にした伸び量の実務的な見積もりや設計への落とし込み手法を紹介します。
熱膨張とは何か?|基礎理論の再確認
固体に熱エネルギーを加えると、原子間の振動が激しくなり、平均的な原子間距離がわずかに増加します。この結果、物体全体が膨張します。この現象を熱膨張と呼び、線的な伸びは以下の式で表されます。
![]()
 :伸び量 [mm]
:伸び量 [mm] :線膨張係数 [1/K]
:線膨張係数 [1/K] :基準長さ(常温時) [mm]
:基準長さ(常温時) [mm] :温度上昇量 [K](℃差)
:温度上昇量 [K](℃差)
※ 線膨張係数 ![]() は材料の種類・組織・温度範囲に依存します。特に樹脂材料や複合材では温度変化に対して非線形な挙動を示す場合もあります。
は材料の種類・組織・温度範囲に依存します。特に樹脂材料や複合材では温度変化に対して非線形な挙動を示す場合もあります。
設計でよく使われる材料の線膨張係数(20 ℃基準)
| 材料 | JIS記号 | 線膨張係数 α [×10−6/K] | 参考温度範囲 [℃] |
|---|---|---|---|
| 一般構造用鋼 | SS400 | 11.7 | 20–80 |
| 工具鋼 | SKD11/61 | 10.8 | 20–80 |
| 銅(純銅) | C1100 | 16.5 | 20–80 |
| アルミニウム合金 | A5052 | 23.1 | 20–80 |
| ステンレス鋼 | SUS304 | 17.3 | 20–80 |
| MCナイロン | — | 80 ※ | 20–80 |
※MCナイロンなどの樹脂は温度変化だけでなく吸湿にも敏感で、寸法安定性に大きなばらつきがあります。
材料別の設計上の特徴
- 鋼(SS400・SKD): 熱膨張は比較的小さく、寸法安定性が高い。工具鋼(SKD)はさらに小さいため精密金型に多用される。
- アルミ合金: 軽量で加工性に優れるが、熱膨張係数が大きく、温度影響を強く受ける。高温環境では対策が必須。
- ステンレス: 錆に強いが、炭素鋼より熱膨張がやや大きい点に注意。締結部の軸力変化に影響する。
- 銅: 電気・熱伝導に優れ、熱膨張も大きい。高温での変位が他材料に比べて顕著。
- MCナイロン: 高膨張かつ温度による変形も大きいため、ベアリング・ガイド用途ではクリアランスを広めに設計。
線膨張量の計算ステップ
- 材質に対応する線膨張係数
 を取得。
を取得。 - 基準長さ
 (常温での寸法)と設計上の温度差
(常温での寸法)と設計上の温度差  を設定。
を設定。 - 式
 に代入して伸び量を計算。
に代入して伸び量を計算。 - 得られた
 をクリアランス設定・基準位置補正などに反映。
をクリアランス設定・基準位置補正などに反映。
実務計算例:SKD金型プレート
200 mm角のSKDプレートが成形工程で80 ℃上昇する場合:
![]()
→ 0.17 mm の伸びを加味し、合わせ面で段差が出ないよう設計初期での補正やスキマ設計が求められます。
熱膨張設計での落とし穴と対策
- 異材ボルト締結: ボルトと母材の熱膨張差により、軸力低下や過剰荷重が生じる場合があります。
- 精密位置決め: 加熱により原点がずれるため、対称構造・中心合わせ・温調配置が有効です。
- 樹脂部品: 高温でのクリープ変形も生じるため、熱膨張と合わせて変形解析が必要です。
- スライド部: クリアランス不足は焼付きや過負荷の原因になるため、最大温度時の拡大クリアランスを考慮。
応用テクニック:誤差を吸収する構造設計
- 浮き支点構造: 熱膨張を一方向に逃がせる設計(片持ち構造など)を用いる。
- スリット・蛇腹部: 拡張を吸収する部材形状を設けることで、全体の変形を局所化。
- 温度センサ・補正機構: 実測温度に応じた補正アルゴリズムを制御側で実装する。
まとめ|温度変化を制する者が精度を制す
装置や金型における高精度化が求められる今日、熱膨張を前提とした設計は、信頼性の高い機械設計を実現するうえで不可欠な視点となっています。使用材料ごとの熱的特性と膨張挙動をあらかじめ把握し、使用環境における温度変化を想定した寸法設計を行うことで、トラブルの未然防止と製品の安定動作に大きく貢献します。
本記事で示した線膨張係数の一覧や計算式は、日々の設計判断における有効な参考情報となるはずです。実機検証やフィードバックと組み合わせながら、熱影響を的確に見越した、より再現性と信頼性の高い設計モデルへと発展させていくことが重要です。